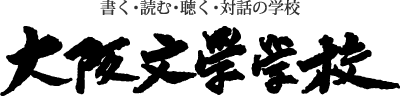第1回 夜・文章講座のご案内。
夜・文章講座
プルーストと小説の諸方法 Ⅰ ――いくつかのパスティシュ(模作)から始める
講師 葉山郁生(作家)
第1回 11月28日(月)午後6時30分~
1回目の課題「ある朝の場面」を書く際に参考にしてほしいプルーストの文章は、次のものです。
朝になると、顔をまだ壁に向けたままで、窓の厚いカーテンの上部にさしこむそとの光線の明暗を見とどけない先から、もう私はその日の天候がどんなであるかを知っていた。表通の最初の物音がそれを教えてくれたからで、湿気が多ければ、物音は、鈍くて、ゆがんでつたわってくるし、晴れわたってつめたく澄んだ朝は、さえぎるものがない、よくひびく地帯を、物音は矢のようにうなりながらつたわってくるので、一番列車のすべりだしの音から、早くも私は、それが雨にかじかんでいるのか、それとも青空に向かってとびたってゆくのかを、ききわけてしまうのだった。もしかすると、それらの物音は、それ自身が、何かもっとすばやい、もっと浸透性に富んだ発散物に先立たれていたのかもしれなかった。そうした発散物は、私の睡眠にしみこんできて、そこに雪を予知する陰鬱な気分をひろげるのだ。あるいはまた、その発散物は、私の睡眠のなかに間歇的に顔を出す一種の小人(こびと)につぎからつぎへと太陽への讃歌をうたわせるので、それらの讃歌が、まだ眠りながらほほえみはじめた私に、とざされたまぶたをすこしずつまぶしさにそなえさせ、ついにびっくりするような歌時計のしらべのなかに私を目ざめさせることになったのだ。
……しばらくのあいだ私は、前記の太陽歓迎のうたい手である私の内部の小人が、彼女〔主人公の「私」が同棲している恋人・アルベルチーヌ〕以上に私を幸福にしてくれるのを知っていて、真先にその小人と向かいあってじっとしているのだった。われわれ個人を構成している諸要素のなかで、われわれにとってもっとも本質的なものは、そんなにひどく目立ったものではないのである。病気がそれらの構成要素を一つまた一つと破壊してしまったあとも、私の内部に、より強靭な生命力をもつものが、まだすこしは残るだろう、とりわけ、二つの作品、二つの感覚のあいだに、ある共通の部分を発見したときにしか幸福を見出さない一人の哲学者が生きのこるだろう。しかしぎりぎりの最後に残るのは、そんな小人ではあるまいかと、私はときどき考えるようになった。それは、コンブレーのめがね屋が天気を知らせるためにショー・ウィンドーのガラスのなかにかざっていたまたべつの小人にひどく似ている。その晴雨計人形は、ちょっと日がさすと、そのカプチン修道士のずきんをぬぎ、雨がふりそうになると、またそれをかぶるのであった。
(『囚われの女』井上究一郎訳)
私は朝早く目をさました、そして、まだ半睡の私にわきおこった歓喜で、私は冬のなかに挿入された春の一日があることを知った。そとでは、瀬戸物接ぎのホルンや椅子なおしのトランペットをはじめとして、晴れた日にはシチリアの牧人とも見える山羊飼(やぎかい)のフルートにいたるまで、さまざまな楽器のためにうまく作曲された民謡の諸テーマが、朝の空気を軽やかにオーケストラ化して、一種の「祝祭日のための序曲」を奏でていた。聴覚、この快い感覚は、街の仲間をわれわれのこもっているところに連れてくる、すなわち、その街のすべての道筋をわれわれに跡づけ、そこを通りすぎるすべての物の形を描き、その色をわれわれに見せてくれるのである。パン屋や乳製品屋の鉄の「カーテン」は、ゆうべは女の幸福を手に入れるあらゆる可能性をしめだしてぴったりとおろされていたのに、いまは、透明な海をわたって走ってゆこうと出帆の準備をしている船の軽い滑車のように、若い女店員たちの夢の舞台にするするとあがってゆくのだった。こことはべつの区域に住んでいたら、人があげる鉄のカーテンのこの音がおそらく私の唯一のたのしみになったことだろう。ここの区域ではほかにもたくさんの音があって私をよろこばせるので、私は朝寝ぼうをして一つでもききのがすのはおしいという気がした。
(同前)