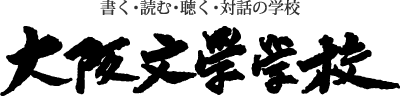第2回 夜・文章講座のご案内。
夜・文章講座
プルーストと小説の諸方法 Ⅲ ――さまざまの時の態様
講師 葉山郁生(作家)
テキスト『失われた時を求めて』第二篇「花咲く乙女のかげに」第一部
課題=「文体上の時の態様」
次の二つの文章を参考に⑴過去形の例、⑵前後は過去形で、その過去の中に入るときは、現在形の例、⑶現在形、ただし過去のことを振り返って語り(手)が現在から事象、真実を述べる形。この三つの時制を一作品で、あるいは短文三つで書いて下さい。
例文「ある日の私――緑の中を歩く」「野火」の文体のうち、この⑴⑵⑶を段落単位で例示しています。
「ある日の私――緑の中を歩く」
⑶緑の中を歩いている。家の近くのただの公園なのだけれど、そこは、街の雑踏から切り離された不思議な空間である。陽に透けて輝く木の葉の向こうにはちらちらと青い空がのぞいている。広い池には、家鴨が二羽、寄りそって泳いでいて、水面はきらきらと光を放ち目にまぶしい。優しい風が公園の隅々までなでていく。そんな空間の中をゆっくり歩いていく。
⑴ある春の日、私は窓の外にひろがる、真っ青な空とれんげ畑に誘われて、散歩に出かけることにした。暖かくなったかと思うと、寒さが戻る春先、私は下宿で何もしたくない日々をすごしていた。その春の一日、まず、れんげ畑の脇を通って、見て匂って楽しんで、あんまり気分がよくなったから、歩いて十五分ほどの自然に囲まれた散歩するには充分な広さの、その公園へと足を延ばすことにした。交通量が多く、たくさんのお店が建ち並ぶ大通りに沿ってどんどん進み、急な坂を上ればそこが公園の入口だった。
⑵その公園は、寺ヶ池公園という名前のとおり、寺ヶ池というため池を中心に整備されている。とても大きな池で釣り人も多く、池の周辺には自然が豊富に残されている。公園の中に入った私の目の前には、透き通った青い空ときらきらひかる水面、それを取り囲む緑の木立の光景がひろがっていた。私は、木々に覆われた散歩道をゆっくりゆっくりと歩き始めた。昨日、雨が降ったせいか、少しひんやりとしていて気持ちいい。木や草たちも余分なものを洗い落としたのかさっぱりとしていて、すがすがしい。しばらく歩いているうちに、頭の中が真っ白になっていた。何も考えずに空っぽのまま自然を体中で感じながら、ただ緑の中を歩いていた。
それまでは、静かだと思っていた。けれど、それは大きな間違いであった。何種類もの鳥の声、木の葉と葉が重なり合うざわめき、そして風の音、ここにいる全ての生き物が自分が生きていることを主張していた。
ふと、郷里の家で飼っていた兎を散歩に連れ出した日のことを思い出した。犬用のキャリーバックから兎を出して、草の上に座らせると、耳をぴくぴく鼻をひくひくさせて、しきりに辺りを気にしはじめた。あの時、きっと兎は、周りから聞こえてくる自然の声に敏感に反応していたのだろう。それは人間の私が感じたものよりももっと鋭く、はっきりとしたものだったに違いない。
自然が私たちにどのような影響をもたらしているのかはわからない。でも、緑の公園にいる人々の周りには、いつもほのぼのとした優しい雰囲気が漂っている。散歩をする老夫婦、犬と一緒にベンチに座ってのんびりしているおじさん、自転車で走り抜ける親子、バドミントンをするカップル、同じ空間の中でみんなとても安らいでいる。それは、自然から受ける同じ心地よさを共有しているということなのだと思う。
私はそんな思いや感じにひたされながら緑の中を歩いていたのだった。
大岡昇平「野火」
⑴死ぬまでの時間を、思うままに過すことが出来るという、無意味な自由だけが私の所有であった。携行した一個の手榴弾により、死もまた私の自由な選択の範囲に入っていたが、私はただその時を延期していた。
熱帯の陽の下に単調に重畳した丘々を、視野の端に意識しながら、私は無人の頂上から頂上をさまよった。
草の稜線が弧を描き、片側が嶮しく落ち込んでいるところへ出た。降りると、漏斗状の斜面の収束するところに木が生え、狭い掘れ溝が、露出した木々の根の間を迂っていた。空谷はやがて低い崖の上で尽き、下に水が湧いていた。
崖の底の一つの穴から、吹き出すように湧いた水は、一間四方ほどの澄んだ水盤を作っていた。私は岸に伏し、心行くばかりその冷い水を飲んだ。
水は細い瀬を作って、次の水盤に移り、また瀬となって、流れ出していた。小さな道が流れに沿って下っていた。私は降りて行った。流れが漸く音を立てるあたりで、道はそれを横切った。
流れは暗い林に入り、道は林を迂廻した。林の奥で滝音が近づき、後になった。不意に水は林を破って迸り、再び道に沿い出した。
⑵死は既に観念ではなく、映像となって近づいていた。私はこの川岸に、手榴弾により腹を破って死んだ自分を想像した。私はやがて腐り、様々の元素に分解するであろう、三分の二は水から成るという我々の肉体は、大抵は流れ出し、この水と一緒に流れて行くであろう。
私は改めて目の前の水に見入った。水は私が少年の時から聞き馴れた、あの囁く音を立てて流れていた。石を越え、迂回し、後から後から忙しく現われて、流れ去っていた。それは無限に続く運動のように見えた。
私は吐息した。死ねば私の意識はたしかに無となるに違いないが、肉体はこの宇宙という大物質に溶け込んで、存在するのを止めないであろう。私はいつまでも生きるであろう。
私にこういう幻想を与えたのは、たしかにこの水が動いているからであった。
(ただし、ここの⑵は、過去形の中に現在形でなく、推量形が入っている)
⑶私がこれを書いているのは、東京郊外の精神病院の一室である。窓外の中庭の芝生には、軽患者が一団一団とかたまって、弱い秋の陽を浴びている。病舎をめぐって、高い赤松が幹と梢を光らせ、これら隔離された者共を見下している。
あれから六年経った。銃の遊底蓋を拭ったままで、私の記憶は切れ、次はオルモックの米軍の野戦病院から始まっている。私は後頭部に打撲傷を持っていた。頭蓋骨折の整復手術の痛さから、私は我に返り、次第に識別と記憶を取り戻して行ったのである。
私はどうして傷を受け、どういう経路で病院に運ばれたかを知らなかった。米軍の衛生兵の教えるところによれば、私は山中でゲリラに捕えられたので、傷は多分その時受けたのだろうという。軍医は私の記憶喪失が、脳震盪による逆行性健忘の、平凡な場合だと説明した。