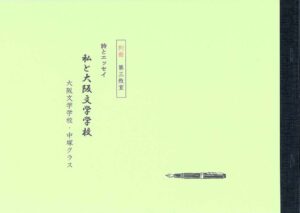通教生の皆さんへ●「文校ニュース」3月1日号のPDF公開
3/9通教部スクーリングの詳細や、24年秋期第2回提出作品総合評などが掲載された「文校ニュース」3月1日号のPDFファイルを公開します。
下記リンクをクリック(タップ)したあと、スクーリング案内チラシに記載していた樹林2・3月合併号(通教部作品集)用の閲覧パスワード(半角数字)を入力すると、ダウンロードできます。
紙の「文校ニュース」は3/2、全通教生に発送します。
【寄稿/種村宏】クラス主催・中塚鞠子チューター送別会 気持ちよく終了する
2月27日(木)、午前11時半から14時30分の3時間にわたって、新大阪ワシントンホテルプラザ23階「チャイナテーブル」の個室において、昼間部詩とエッセイ担当・中塚鞠子チューターの送別会がクラス主催で開催された。当日の参加者は、現役16名(3名欠席)、OB3名にチューターを入れて20名だった。送別会当日は、このところの寒波も去って、23階の窓辺からの眺望は、ゆったりと流れる淀川や大阪都心のビル群にかけて春霞がかかる。送別会としては、絶好の好天に恵まれた。
型通りの挨拶・乾杯(乾杯の音頭は大原素子)の後2時間、ゆっくり中華料理をいただきながら談笑した。その後、持ち寄った『第三教室』別冊「私と大阪文学学校」に目を通しながら、一人一人、辞められる中塚チューターへのお礼の言葉と日々学んだ思いを述べた。また、山本瑛子が、餞別を手渡した。
中塚チューターからは、お礼の言葉のあと、私は、皆さんが詩を書くことが嫌いになることが無いように、各人の個性は違うのだから、それを作品に生かせば良い、との主旨の話があった。また、皆さんから作品を通じて、実に多様な生き方を見せてもらった、勉強になったとも述べられた。
チューターが辞められるに伴い、クラスを替わる人、卒業する人、休学する人が出た。新学期からは、新しいチューターの元、気も新たに学びたい。ことわざに、逢うは別れのはじめとあるが、その時はその時と思う他あるまい。幹事は、川本順子、種村宏でした。(文責・種村宏)
//////////////////////////
≪小原より≫
中塚鞠子さんは、2006年春期からずっと昼間部(木曜日)のクラスを担当してこられました。この3月をもって、年齢・体調面からチューターを退任することになりました。4月からは、現在“昼・詩入門講座”を担当されている近藤久也さんが中塚クラスを引き継ぎます。
今日、二人の新入生。春期[4/6入学式]新入生は20名に達する!★福井県坂井市の78歳女性が読売新聞をみて通教部・小説クラスへ★大阪市の54歳男性が7年半ぶりに夜間部・小説クラスへ再入学
★いきなりオンラインで届いた、福井県の女性の「入学申込書」には次のように記されていいました。
【相手に伝える言葉、また相手の言葉を的確に把握し返答することが大変不得意である事に気がついていました。そんな折り、2月中旬の読売新聞に大阪文学学校の事が紹介されており、考えながら書くことによって私の不適切な話し言葉が是正されるのではないかと思いまして申し込みました。】
影響を受けた作品・作家は、【夏目漱石「夢十夜」 芥川龍之介 三浦哲郎】とのこと。
◎今日の夕方、電話をしてみました。今まで小説を書いたことはないとのことでしたが、言葉少ないながらも意欲的な方で、3/9通教部スクーリングを見学しに文校にやって来るとのことでした。
★大阪市の男性のオンラインによる「入学申込書」には、次のように書かれていました。
【いぜん文校に通ってたのですが、またやってみようと思いました。古代史に興味があるので、そのあたりを書ければと思っています。専科は修了しているので、平野クラスに入れるでしょうか?】
影響を受けた作家として、【村上龍、中上健次、坂口安吾、チャールズ・ブコウスキー】の名前をあげていました。
◎過去の在籍カードを繰ってみると、男性は2014年10月から17年9月まで3年間、夜間部・小説クラス(小原c⇒尼子c⇒平野c)に通っていました。
電話をしてみました。やはり、思っていた人でした。平野クラスでスタートすることにOKを出しました。
(小原)
《2/21》通教部生へ『樹林』25年2・3月合併号(通教部作品集)を発送!◆3/9通教部スクーリングの見学(Zoom可)を希望される一般の方にも、『樹林』2・3月合併号をお届けします。ご連絡ください。

【『樹林』25年2・3月合併号(通信教育部作品集)の目次。作品名と作者名がズラッと並ぶ】
214ページ立ての『樹林』25年2・3月合併号は、先週の金曜日(21日)昼に印刷所からが仕上がってきました。
そっこく、北海道から沖縄まで全国40都道府県にまたがる通教部の皆さん(127名)と通教部チューター12名に発送しました。今日(25日)あたり、ほとんどの方のところには着いているかと思います。
『樹林』2・3月合併号は、3月9日(日)通教部スクーリングの合評テキストになります。該当クラスの作品をしっかり読んで、合評会に臨んでください。感想をメモしておくことをお薦めします。
郵便到着が遅くなっていることを考慮して、『樹林』2・3月合併号のPDFを2/20文校ブログで公開しています。こちらも活用してください。
●『樹林』2・3月合併号を手にして気づかれた方がいらっしゃるかと思いますが、いつもと違って背表紙になにも書かれていません。印刷段階における製本ミスです。印刷所は、急ピッチで刷り直すことになりました。木曜日(27日)に背表紙の入ったものが仕上がってくることになっています。
その27日以降、昼・夜間部の皆さんには教室でお配りします。
また、休学生や定期購読の皆さんへの発送と、元チューターなど文校関係者や新聞社、出版社、図書館への寄贈は、27日以降になります。
●通教部生の皆さんへは、まもなく発行する「文校ニュース」といっしよに、背表紙入りの新しい『樹林』2・3月合併号をお届します。
■『樹林』2・3月合併号に自分の作品が載っていて講読を希望される方は、事務局まで何冊でも申し込んでください。1冊650円です。すぐお送りします。
■3/9スクーリングの見学(Zoomでも可)を希望される一般の方へも、ご連絡いただければ、『樹林』2・3月合併号をお送りします。
(小原)
■【文校教室】公開/昼・詩入門講座[担当;近藤久也さん]に15名参加。愛知の夜間部生・中本さんも■【読売新聞大阪本社】朝井まかてさんがゲストの“読書サロン”に文校関係者が20名近く参加。事務局の小原も。
■午後3時から5時45分まで、公開/昼・詩入門講座(秋期最後・3回目)がおこなわれました。作品提出13名中12名出席。参加者15名のうち、一般2名。
講座の初めに近藤講師<4月からは昼間部/詩・エッセイクラスも担当>から、村野四郎の詩「鹿」「棒高飛」について、10分ほど話がありました。
その後近藤講師は、事前にプリントを配布してあった提出作品13編について1編ずつ懇切で鋭い批評をくわえていきました。
恒例となっている“私がいいと思った作品”として2編の発表もありました。提出13編の中から選ばれたのは―――◇朽葉充「宝石」 ◇名倉弓子「朝の風景」。来期、朽葉さんは昼間部・近藤クラスへ、名倉さんは昼間部・小説・金曜日クラスのチューターへ。
■文校から3つ目のメトロ駅「南森町」近くの読売新聞本社ビルの地下1階ギャラリーで、朝井まかてさん<直木賞作家/文校修了生>の“よみうり読書サロン”がありました。午後2時から3時30分過ぎまで。その後、朝井さんの著作の購入者を対象としたサイン会がありました。
ぼくも、午後1時30分に文校を抜け出し行ってきました。マスクをしている人が多く、しっかりとは確認できませんでしたが、全参加者80中、文校在校生やOBが20名近くいたのではないでしょうか。今日・土曜日のクラスゼミを1時間繰り上げてもらって参加できた大西クラスの若い女性二人、昼・火曜・佐伯クラスの男女3人など・・・・・・。
朝井さんは読売新聞記者の問いかけに答えるかたちで、1/31読売新聞<朝刊>に掲載されていた、書き下ろしの掌編「約束」(9枚)に込めた想いを語りました。さらに、今までの著作約20冊を網羅しながら、それぞれの作品世界を垣間見せてくれました。また、文校時代のエピソードも披露されました。会場から、質問・感想を求められたとき、ぼくや幾人かの文校生もマイクをにぎりました。
サイン会の始まる前に、ぼくは会場を後にし文校に戻りました。
朝井さんの思いやりのある人柄にふれ、さまざまな作品を書いていることを知れた貴重な場になったのではないでしょうか。
朝井さんが、こんど文校にみえられるのは、4月6日(日)入学開講式です。20分ほど話をしていただきます。春期新入生だけでなく、在校生も参加できます。それまでに、できるだけ多く朝井さんの著作を読んで、朝井さんと話する機会を持てるようにしませんか。
(小原)