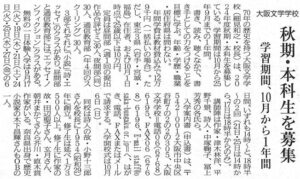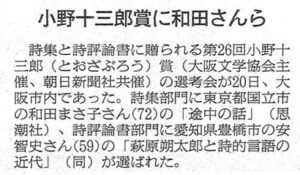【一挙に入学者4名】神戸市・61歳男性が通教部へ、大阪府熊取町・66歳男性が通教部へ、奈良県斑鳩町・55歳女性が昼間部へ、宮崎市(近々大阪に移住)・30歳男性が夜間部へ。◆今日の体験入学(オープンキャンパス)に、昼・夜あわせて10名参加(うちZoom4名)。◆明日(25日)・5回目の体験入学は午後2時~。担当講師は谷良一さん(ノンフィクション作家)。飛び入り歓迎。
今日の一日体験入学は昼の部に3名(うち宮崎市からZoom1名)、夜の部に7名(うち愛媛県西条市などからZoom3名)の参加がありました。
体験入学(オープンキャンパス)は、3月17日を皮切りに今日(24日)まで4日間にわたって、昼・夜別に計6回催してきました。あとは、25日(水)の[昼の部]、27日(金)[昼の部]と[夜の部]を残すのみとなりました。
★きょう入学された4名を紹介します。
【 】内は、入学申込書の中の「入学のきっかけ・書きたいテーマなど」欄からの引き写しです。“ ”内は、影響を受けた作家・詩人名、です。≪ ≫内は、文校のこと(あるいは秋期生募集)を何で知りましたか、という問いかけへの答えです。
入学申込書で記載のない箇所は、そのまま記載しません。
◆神戸市の男性は通教部・小説クラス希望で、長いものに挑戦しているとのこと。
【推理物・怪奇物・ファンタジー物を読み、自作小説を書いていたので、入学したいと思った。】
“西村京太郎(十津川シリーズ)”
≪朝日新聞≫
◆熊取町の男性は、通教部・エッセイ/ノンフィクションクラスを希望。
◆斑鳩町の女性は、文校のことは20年前から知っていたとのこと。今日の体験入学・夜の部を終えた直後、夜間部・小説・西村クラスへ入学を申し込む。
◆宮崎市の男性は、文校に通うために大阪へ引っ越してくることになった。夜間部・小説クラス(金)を希望。引っ越し先はまだ決まっていないが10月中旬、関空に降り立つチケットを買ったとのこと。≪どなたか、文校に通いやすく、かつ家賃の安いアパートを知りませんか――と、彼が体験入学のとき、Zoom上で呼びかけていました≫
【今年で三十になりますが、いい加減、書くことに真面目に向き合いたいと思い、何かいい方法はないかと「小説 スクール」などと検索し、有象無象の小説教室がひしめきあうネットの海をさまよい続けておりました。
数日前たまたまここのホームページに行き着き、合宿の記事が目に入りました。城の前で撮られた集合写真を見て、大学の頃の楽しかったゼミ合宿を思い出し、ほかの小説スクールとは全く違う印象を受けました。
サイト内で学習システムなどを拝見しても、講師から一方的に小手先だけのテクニックを教えてもらうようなものではなく、生徒が書いた作品について屈託のない意見を交わし合うことがメインになっていて、まさに、大学の頃の研究室と一緒だ!と思い、「ここしかない!」と、すぐに入学を決めました。
現在、宮崎に住んでいるので、学校の近辺でアパートと仕事を探す予定です。
書きたいものは漠然とあるのですが、いろいろ考えすぎて自分はなにが書きたかったのかわからなくなってしまいました。
助けてほしいです(笑)。】
“田山花袋「蒲団」 中島敦「山月記」「悟浄出世」”
≪ネットサーフィンの末、ホームページから≫
(小原)
9/17奈良新聞・暮らし面に“文校・秋期生募集”の記事
今秋3回目の体験入学〔昼の部〕に5名(うち宮崎市からZoom1名)。◆体験後に1名が入学手続き。◆4回目の体験入学(オープンキャンパス)は、24日(火)午後2時からと午後6時30分から。お気軽にどうぞ。予約なしの飛び入り参加も歓迎!

【今日の体験入学〔昼の部〕に5名参加(うち宮崎市からZoom1名)】
大阪文学学校へ入学を希望されている方を対象とした一日体験入学(オープンキャンパス)。今日は昼の部<Pm2~4>のみで、担当は小説クラスの大西智子チューターでした。
教室参加は、9/8通教部スクーリングをZoomから見学された茨木市の女性など4名。Zoomから参加された宮崎市の30歳男性は、近々文校の近くのアパートに引っ越してくるつもりだそうです。もちろん、文校に入るために。
愛知県などから、在校生4名が応援に駆けつけてくれました。
今日はまず、5年前(2019年)の9月にNHKテレビ大阪が関西エリアで放送した“文校の合評会模様”のビデオを7分間ほど見てもらいながら、文学学校の歴史や現状、文校名物の“合評”について、事務局から説明がおこなわれました。
その後、なぜ文校に関心を持ったのか、実際作品を書いているのか、などを中心に参加者各々に自己紹介をしてもらいました。
それから、クラス生の書いた掌編小説(400字詰換算4枚)をテキストにして、大西チューターの仕切り役・助言役で鋭い意見も飛び出す合評会をくり広げました。
さらに、質問に答える形で、文校の学習システムやカリキュラムの説明をおこないました。質問が続出し、予定を10分超過して終了しました。
今日の体験入学で、文学学校のおおまかな形や雰囲気をつかめてもらえたのではないでしょうか。
◆只今開催中の“体験入学”は今後、9月24日(火)昼・夜、25日(水)昼、27日(金)昼・夜に持ちます。24日の予約は7名から入っています。予約がなくても参加できますが、できれば事前に電話かメールをください。すでに入学手続きを終えている方、一度参加されている方も歓迎します。
◆“体験入学”には、オンライン(Zoom)でも参加できます。メールで事前連絡をください。Zoom招待状と合評作品をお送りします。そして、その日の体験入学が始まる30分前にミーティングルームを開きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・
●体験入学のあと、今日の担当講師だった大西さんのクラス(土曜/昼/本科小説)へ入学を決められたのは、兵庫県加西市の45歳女性。
いただいた「入学申込書」の“入学のきっかけ”欄には、【おもしろそうだと思ったからです】とありました。
“影響を受けた作家”として、【桜庭一樹、西加奈子、凪良ゆう】の名前をあげています。
“文校(募集)を知った”のは、【朝井まかてさんのネットの記事】だそうです。
(小原)
【今日・9/21(土)】朝日新聞<朝刊>社会・総合面<23面>・・・第26回小野十三郎賞〈詩集部門〉に和田まさ子さん、〈詩評論書部門〉に安智史さん
◆賞金は、和田まさ子さん、安智史さん、ともに30万円です。
11月16日(土)午後1時半より行なわれる第26回小野賞贈呈式において、賞金は授与されます。

【写真/きのう大阪文学学校でおこなわれた“受賞の記者発表”】
中央奥は、小野賞事務局の高田文月
左側手前より、最終選考委員の葉山郁生(詩評論書部門)、添田馨(同)、冨上芳秀(同)、細見和之(詩集部門)、四元康祐(同)、犬飼愛生(同)
右側は、臨席した朝日新聞、共同通信、読売新聞。事前問い合わせのあった大分合同新聞、福井新聞ほかの各新聞社にはFAXを流す。
◆大阪文学学校発行の文芸誌『樹林』12月(秋期)号で、第26回小野十三郎賞の受賞者(二氏)の「受賞の言葉」や詩部門・詩評論書部門それぞれの選評(六氏)を掲載します。
(小原)
第26回小野十三郎賞(詩集部門、詩評論書部門)きまる。
さる7月10日をもって締め切った第26回小野十三郎賞には、全国各地から詩集120冊、詩評論書5冊の応募がありました。第21回から詩集部門と詩評論書部門に分けて選考していますが、各々に正賞(賞金各30万円)を設けています。予備選考委員は、高田文月、冨上芳秀、中塚鞠子、平居謙、細見和之、松本衆司の6氏で、2回にわたる予備選考を行いました。
本日(9/20)午後1時から、共催をいただいている朝日新聞社の協力を得て大阪市内で、最終選考会を実施しました。最終選考委員(詩集部門 細見和之、四元康祐、犬飼愛生/詩評論書部門 葉山郁生、添田馨、冨上芳秀)の6氏により、最終候補の詩集13冊、詩評論書3冊について、詩集部門、詩評論書部門ともに2時間近くにおよぶ討議の結果、以下のとおり決定しました。
《第26回小野十三郎賞 詩集部門(賞金30万円)》
●詩集『途中の話』(思潮社 刊)
和田まさ子(わだ・まさこ) 東京都
《第26回小野十三郎賞 詩評論書部門(賞金30万円)》
●詩評論書『萩原朔太郎と詩的言語の近代』(思潮社 刊)
安智史(やす・さとし) 愛知県
〔授賞理由〕
●詩集部門● 和田まさ子さんの『途中の話』は、地名と日本近代文学の作者名をブイのように用いて、日本の現在の危うい姿を浮かび上がらせている。これは詩にしかなし得ない表現として高く評価された。非人間的な視点を導入している点も注目を集めた。
●詩評論書部門● 安智史さんの『萩原朔太郎と詩的言語の近代』は、萩原朔太郎の詩業をめぐる各論をていねいに積み上げ、その全体像を描くとともに、萩原恭次郎、丸山薫、中原中也らとも関連づけ、近・現代詩史の一つの系譜をあとづけた詩評論書の力作として評価した。
選考会のあと大阪文学学校に場を移し、午後4時30分から受賞の記者発表をおこないました。臨席したのは朝日新聞、共同通信、読売新聞。ほかの新聞社にも、受賞決定のFAXを流しました。
詳しくは、小野賞を共催していただいている朝日新聞の明日(21日)の朝刊(社会面)をご覧ください。
なお第26回小野賞贈呈式は、きたる11月16日(土)午後1時半より、大阪市北区の中之島フェスティバルタワー12階・アサコムホールにおいて行います。
◆小野賞を主催しているのは、大阪文学学校の運営母体である一般社団法人・大阪文学協会(代表理事;葉山郁生)。小野十三郎さんは、大阪文学学校創立の1954年から91年まで校長を務め、96年10月に93歳で亡くなるまで名誉校長でした。
(小原)