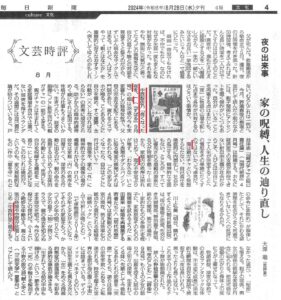通教部生・休学生などへ『樹林』8・9月合併号(通教部作品集)を発送!◆9/8通教部スクーリングの見学(Zoom可)を希望される一般の方にも、『樹林』8・9月合併号をお届けします。ご連絡ください。★昨日(月)の夜・文章講座[担当;津木林チューター]の参加者は作品を事前提出していた18名。作品を提出しながら2名が欠席。

【『樹林』8・9月合併号(通信教育部作品集)の目次。作品名と作者名がズラッと並ぶ】
212ページ立ての『樹林』8・9月合併号は、昨日(月)昼に印刷所から仕上がってきました。
そっこく、真銅・事務局員が台車で谷町郵便局に運び込み、北海道から沖縄まで全国40都道府県にまたがる通教部の皆さん(137名)と通教部チューター12名に発送しました。
『樹林』8・9月合併号は、9月8日(日)通教部スクーリングの合評テキストになります。該当クラスの作品をしっかり読んで、合評会に臨んでください。感想をメモしておくことをお薦めします。
郵便到着が遅くなっていることを考慮して、『樹林』8・9月合併号のPDFファイルを8/21文校ブログで公開しています。こちらも活用してください。
また、休学生の皆さん(90名)にも郵送し、元チューターなど文校関係者や、新聞社、出版社、図書館へも寄贈しました。
休学生へは、<24年度秋期/進級(継続届)>用紙と<速報! 『樹林』在特号掲載作品決定>チラシを同封してあります。――その二つは、通教部生へはお送りしてあります。
定期購読の皆さん(38名)へは、「文校ニュース」8月8日号を添えて、『樹林』8・9月合併号を発送しました。
昼間部、夜間部生の皆さん(161名)は、クラスゼミで来校のおり、教室の机の上から『樹林』8・9月合併号を持ち帰ってください。Zoomで合評に参加している皆さんへは、後日郵送します。
●『樹林』8・9月合併号に自分の作品が載っていて講読を希望される方は、事務局まで何冊でも申し込んでください。1冊650円です。すぐお送りします。
●9/8スクーリングの見学(Zoomでも可)を希望される一般の方へも、ご連絡いただければ、『樹林』8・9月合併号をお送りします。
(小原)
今夕(28日)の毎日新聞の“文芸時評”欄(評者;大澤聡)で、中西智佐乃さん(文校修了生)が『すばる』(集英社)9月号で発表した小説「長くなった夜を、」が大きく取り上げられる!
中西智佐乃(なかにし・ちさの)さんは2018年3月まで長い年月、大阪文学学校の昼間部や夜間部に在籍されていました。
中西さんは19年10月、応募総数1972編の中から、小説「尾を喰う蛇」(230枚)で第51回新潮新人賞を受賞されています。その受賞作は、『新潮』19年11月号に掲載されました。
その後、『新潮』21年8月号に「祈りの痕」(180枚)、『新潮』23年2月号に「狭間の者たちへ」(160枚)を発表しています。
23年7月、新潮社から刊行された単行本『狭間の者たちへ』には、「狭間の者たちへ」と「尾を喰う蛇」の2編が収められています。
※2023年7月1日・文校ブログ参照。
●新潮社のサイト
【第51回新潮新人賞 受賞者インタビュー 暴力を追いかける/中西智佐乃】
から以下に、大阪文学学校について述べている箇所を抜粋して紹介します――――
≪中西さんの個人的・文学的来歴を教えてください。≫
特に不自由なく、幼稚園から大学まで通わせてもらい、会社に就職することが出来ました。小説は十代の頃から何年かに一回、短いものを書いていましたが、ちょっと思い出しただけで顔から火が出そうなぐらい酷い出来でした。その後社会人になって改めて推理小説を書きましたが、これも相当酷いものでした。それから二年くらい一人で書いていたのですが、朝ドラ「芋たこなんきん」を見た母から大阪文学学校を勧められ、確かに一人でやっていてもよく分からんと、入学しました。雑居ビルにある教室前の廊下が「大丈夫か?」と思うぐらい暗くて不安になりましたが、そこに通ったことで今作が書けました。実践重視の学校で、とにかく書かされる。長いもので一〇〇枚程度を二、三か月に一作、年間で四本を仕上げました。合評ではめちゃくちゃ叩かれますし、時々褒められることもありつつ、でもやっぱりめちゃくちゃ叩かれました。体力的な問題から二年くらいで一旦辞めて、そこから四、五年書きませんでした。プロになるどころか、もう書かないかもしれないとすら思いました。そのくせ仕事が落ち着いて心や身体が元に戻ってきたら、いけしゃあしゃあとまた書きたくなった。自分の決断なんてその程度だよなと思いました。ひとまず趣味として、ぼちぼちやっていこうと、二十代の終わりに大阪文学学校に入りなおしました。
復帰して一作目が、やはり酷評され、「次、みとけよ」という闘志というか、怒りが湧きました。二作目を読んだ先生と生徒さんに新人賞に応募をするよう勧められ、今に至ります。はじめはメフィスト賞はじめエンターテインメントの賞に応募していたのですが、アドバイスを受けて純文学系の賞に応募すると予選を通過して、自分の方向性が分かりました。・・・・・・・・・
(小原)
【今日も2名の秋期入学申込あり!】岐阜県の66歳女性、千葉県の28歳男性がともに通教部・小説クラスへ!◆お二人とも、事前の連絡はなく、いきなりオンラインで入学申込書がとどきました!
★きょう入学されたお二人を紹介します。
【 】内は、入学申込書の中の「入学のきっかけ・書きたいテーマなど」欄からの引き写しです。“ ”内は、影響を受けた作家・詩人名、です。≪ ≫内は、文校の学生募集を何で知りましたか、という問いかけへの答えです。
◆岐阜県関市の女性◆
【二十代最後の年に、中日文化センターの小説教室を受講し、その受講生中心に同人文芸同人誌が発刊され数年在籍したが、出産後余裕がなくなり退会、三十年余りが経った。娘二人が嫁ぎ、再び同人誌活動を始めたが、小説や文芸の基礎や知識の不足を痛感し、改めて勉強をしたいと思うようになり、入学しようと思いました。
書きたいテーマは特に何というものはありませんが、いろいろな人間模様を書きたいと思います。】
“三浦綾子”
≪同人誌仲間で大阪文学学校で学んでいる方がいらっしゃって、インターネットで調べ、秋期募集を知りました。≫
◆千葉県柏市の男性◆
【純文学の五大新人賞で受賞して小説家デビューをしたいから。
テーマは生死、孤独、など切実なものについて書きたいです。】
“中村文則、朝井リョウ、村上春樹、石田衣良”
≪新潮新人賞 中西智佐乃さんの受賞インタビュー≫
(小原)
きょうの昼・詩の連続講座に、作品提出18名を含む20名が参加。■最終的に締切った「読書ノート」提出者は、54名に。コロナになった直後(20年5月)に次ぐ提出数。
◆春期3回目の公開/昼・詩の連続講座(担当;近藤久也さん)は、午後3時からも持たれました。
講座の初めに近藤久也講師から、詩人・杉本真維子さんの詩作品「五百円」を見本に、“生々しい言葉の詩の力”についての話が10分ほどありました。
その後近藤講師は、事前にプリントを配布してあった提出作品19編(欠席1名の作品はのぞく)について1編ずつ懇切で鋭い批評をくわえていきました。作者に創作の意図をたずねたり、会場から意見を求めたりしながら。
また、今回の19編の中で“私がいいと思った作品”として3編を挙げられました。―――名倉弓子(通・飯田c)「蝉は夏に」、三村あきら(通・高橋c)「生々しい」、国津洋子(夜・休学中)「ラブコール」。
終了したのは、午後6時30分。近藤講師が担当するようになった23年春期からの計9回の中でもっとも長丁場の〈3時間半〉を記録しました。
◆締切を1週間延ばした24年春期の「読書ノート」の提出者は、54名まで伸びました。この猛暑の中、頑張った人が多く、コロナになった直後(20年5月/昼・夜間部のクラスゼミを休止せざるを得なくなったため例年の8月を前倒し)に次ぐ提出数を記録しました。
◎ちなみに過去の提出数を列挙すれば、前回(24年2月)――46名、前々回(23年8月)――50名、(23年2月)――46名、(22年8月)――52名、(22年2月)――44名、(21年8月)――50名、(21年2月)――58名、(コロナで前倒し・20年5月)――60名、(20年2月)――27名、(19年8月)――30名、となっています。
コロナの時代になってから、提出率がグーンと上がってきているのが分かります。
●津木林洋チューター担当の8/26「文章講座(夜)」の作品提出はすでに締め切っていて、20名から提出がありました。
作品を提出していない人も参加できます(在校生無料)。
●冨上芳秀チューター担当の9/2「詩の連続講座(夜)」の作品提出は今日、締め切りました。岐阜県各務原市の通教部生(泊り掛け)をふくむ13名から提出がありました。
(小原)
【この1週間に秋期新入生3名誕生!】神戸市の50代前半女性が通教部へ、大阪市の50代前半女性と30代前半女性が夜間部へ。
★16日(金)から昨日(22日/木)にかけて、入学された3名を紹介します。
【 】内は、入学申込書の中の「入学のきっかけ・書きたいテーマなど」欄からの引き写しです。“ ”内は、影響を受けた作家・詩人名、です。≪ ≫内は、文校の学生募集を何で知りましたか、という問いかけへの答えです。
◆16日(金)。文校に直接やって来て、入学手続きをされた神戸市の女性は、通教部・小説クラスへ再入学。2018年4月から1年間夜間部に在籍されていて、その間に小説が『樹林』在特号に選ばれて載っています。
【前回、本科での1年が楽しかったからです。】
◆21日(水)。オンラインで入学申込書を送ってこられた大阪市の50代前半女性は、それまでひと月の間に3度、夜間部の各クラス(詩・エッセイC②、小説①)を見学されていました。その上で、木曜日・夜の詩・エッセイCを希望されました。小説を書きたい気持ちも強く持っている方です。
【「書く」ことが好きというより、自分にとって「食べたい」や「眠たい」と等しい感覚で、それは衝動的に「書きたい」という欲求に従って書いているように思います。小学生の頃から。
自分らしさを表現するのが「話す」より「書く」ほうが、思いを上手く伝えられるような気もしています。
ただ「書きたい」と思うところから、アートエッセイを書くようになり、次第に図録文章やアーティストから案内状文章を依頼されるようにもなりました。
お褒めの言葉をいただき、書き切れて良かったと思う反面、「書きたい」だけの欲求だけでは書くことのできない苦痛を伴うこともあるのだーと依頼されたことで初めて得た経験もあります。
そこから縁が縁を呼び、自作詩を朗読表現するイベントを主催、また作家のグループ展やアートプロジェクトにお声掛けいただき、詩を題材とした作品づくり、ギャラリーでのアーティストトークショーにゲスト参加依頼もあり、「ことばを紡ぐ表現者」として活動しています。
ーと、ここまで自分自身の感性だけでやってきましたが、才能豊かな方々との出会いもあり、更に向上していきたい、そのためにはやはり学び舎が必要なのではーと思うようになりました。
そんな話を友人や知人にしてみた折に、こちら大阪文学学校を勧められました。
見学もさせていただき、切磋琢磨される合評の雰囲気も面白いと感じ、入学してみたいと思い至りました。】
“金子みすゞ、茨木のり子”
≪友人や知人 インターネット≫
◆22日(木)。2020年10月から3年間、昼間部や夜間部の小説クラスに在籍されていた大阪市の30代前半女性から朝方、オンラインで「入学申込書」が飛び込んでいました。在籍時、学生委員会の活動にもかかわっていました。金曜部・夜・小説・専科研究科(谷口クラス)希望です。
【2020-2023で3年間在籍していて、また入学したくなったため。】
“絲山秋子、江國香織、柳美里、西村賢太、中島らも、原田宗典など”
(小原)