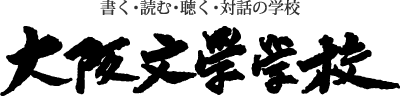第2回 夜・文章講座のご案内。
夜・文章講座
プルーストと小説の諸方法 Ⅱ ――プルーストに倣った物と人と空間のデッサン
講師 葉山郁生(作家)
◎内容
・『スワン家のほうへ』第二部前半の通読
・課題=「人を描く」(人称・題材自由で、人物の身体部位や顔を、一回目の物のように細部で描く) 例文として『失われた時…』第二部のオデットの顔その他を描いた文章。またフローベール『ボヴァリー夫人』の身体と顔を描いた文章
* *
二回目の課題文のための例文を以下に掲げます。
A、Bはプルーストのスワンから見たオデットの顔、姿を描いた文章(ロマネスク的、観念連合的な愛)、Cはフローベールのボヴァリー夫人の身体を描いたリアリズム的表現です。どちらか(あるいは両方も可)で、顔、身体のデッサンを描いてください。
【A】
彼女は見事に刺繍をほどこした布をコートのように胸の上でかき合わせながら、モーヴ色のクレープ・デシンの化粧着姿で彼を迎えた。彼のそばに立ち、ほどいた髪を頬づたいにすべらせ、楽々と版画のほうにかがめるように軽く踊っているような姿勢で片足を曲げ、気がひき立たないときの疲れをおびてしずんだ大きい目で、顔をかしげながら版画に見入っている彼女は、システィナ礼拝堂の壁画(後のボッティチェルリの作品)にあるイェテロの娘のセフォラの顔に似ていることで、スワンをおどろかせた。
(…………)
おそらく彼がしばらくまえからもつようになった印象の豊かさが、その豊かさはむしろ音楽への愛好と一緒にやってきたとはいうものの、絵画に対する彼の趣味を高めたので、この喜びは一段と深くなり、永続的な影響をスワンに及ぼしたものに違いなく、いま彼はこの喜びを、オデットとサンドロ・ディ・マリアーノの作になるセフォラとの類似のなかに見出したのだ(ボッティチェルリという綽名が、この画家の真の作品を思い出させるかわりに、彼についてのいまはやりの、卑俗で間違った観念を思い出させるようになって以来、世人はこのサンドロ・ディ・マリアーノに好んでこのよく通った綽名をつけている)。だから彼はもはやオデットの顔を、彼女の頬の多少とも美しいところとか、いつか彼女を抱擁して自分の唇をそこにつけるときに見出すに違いないと思い描いている、あの完全に肉色をしたやわらかさなどから評価しなくなり、むしろ彼女の顔を、繊細で美しい線の錯綜として評価し、その錯綜を目でさばき、その渦巻く曲線をたどり、襟首の調子をあふれ出る髪の毛やまぶたのたわみと一つに合わせながら、つまり彼女を、彼女の特徴が明らかに理解されるような肖像画のなかに入れこんで見るようになったのだ。
彼は見つめた。壁画の断片が彼女の顔とからだから現われた。そしてそのとき以来彼はオデットのそばにいるときも、ひとりで彼女のことを思っているときも、常にこの壁画の断片を彼女から見つけ出そうとした、そして彼がフィレンツェ派の傑作を尊重したのは、むろん、彼がそれを彼女のうちに見出したからには違いないが、この類似によって彼は彼女にもまた美しさを認め、彼女をいっそう大切に思ったのだ。
【B】
ふだん他人はわれわれに対してひどく冷淡な存在だから、もしわれわれがそんな他人ひとりのなかに苦しみや喜びを汲み出すことのできる力を感じるとき、その他人はわれわれにとって別な宇宙に属しているように思われる、彼は詩でつつまれている、彼はわれわれの生活をおどろくほど広くし、いわばそのひろがりのなかで、われわれは多少とも彼に近づいてゆくのである。スワンはやがて訪れる数年のあいだに、オデットが自分にとってどういうものになるかということを、不安なしには考えられなかった。時として、こうした冷たい美しい夜々、彼の眼と人気のない街々とのあいだに光をふり注ぐ皓々とした月を、その無蓋二人乗馬車のなかから眺めながら、彼はこの月の面のように明るくて、ほんのり薔薇色にそまったあの別な顔、あの日彼の思念のまえに浮かび上がり、そしてそれ以来、彼の日々に、神秘な光を投げかけ、その光のなかで彼が見つめるあの顔を思うことがあった。オデットが召使たちを休ませてしまったあとに彼が着くとき、彼は小庭の門の呼びりんを押すまえに、まず通りに下りて、隣りの家々のそっくり同じだが、いまは明りのない窓のあいだに、ただ一つ明るく残っている彼女の一階の部屋の窓が、その通りに面しているところへ行く。彼は窓ガラスをたたく。すると、それと知って彼女は答え、反対側の入口へ行って彼を待つ。
【C】
シャルルは彼女の爪の白さにびっくりした。つややかに光って先が細く、ディエップの象牙細工よりもっときれいにみがかれ、先端をまるく切ってある。手はそんなに美しくない。白さがたりないのだろう、そして関節のところがややぶこつだ。また少し長すぎて、輪郭に曲線のやわらかみがなかった。いちばん美しいのは目だ。茶褐色だのに睫毛のせいで黒く見えた。まなざしは無邪気な大胆さでまっこうからあけすけにじっと見る目だった。
手当がすむと医者はルオー氏自身の口から「ちょっと一口召し上がってからお帰りを」とすすめられた。
シャルルは階下の食堂へ行った。二人分の食器に銀のコップをそえ、小テーブルにおいてある。テーブルは、トルコ人を模様にしたインド更紗をかけた天蓋つきの大きなベッドのすそにあった。窓とむきあった高い樫材の箪笥からはイリス香料とまじったシーツの匂がやってきた。部屋のすみずみに小麦の袋が地べたに立てならべてある。これは石段三つで行ける穀物倉にはいりきらない分だ。はげて白っぽくまだらのできた緑塗りの壁のまんなかに、この部屋の装飾のつもりらしく、黒鉛筆で描いたミネルヴァの顔が金縁の額にはめて釘にかけてあって、絵の下のほうに《お父様に》とゴチック書体で書きいれてあった。
まず病人の話、つぎに最近の天気のこと、きびしい寒さ、夜になると野原によく出る狼のうわさ、そんな雑談をする。ルオー嬢はこのごろは自分ひとりで農場の世話をさせられているから田舎でおもしろい目などしていないといった。食堂がひえびえして彼女は食べながらふるえていた。そのとき、黙っているときはかるくかむ癖のある肉のあつい唇が少しあらわれるのだった。
白い折襟から頸筋が出ていた。髪はきれいな細い線でまんなかから分け、両側の黒髪はなめらかでそれぞれ一つにぴったりとくっついたようだ。分けた筋は頭の曲線どおりにかるくくぼんでいる。なお、髪は耳たぶをちょっと見せ、額の両ぎわのところで田舎の医者がはじめて見るようなウェーブをつくって、うしろのゆたかな髷と一つになっている。頬はばら色だった。まるで男のように胸のところの二つのボタンのあいだにべっ甲の眼鏡をさしていた。