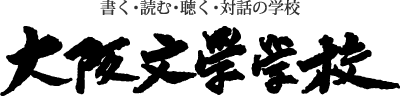在校生の作品
掌編小説「ガラガラ」
この銭湯では年に四回、つまり、三ヶ月に一度、福引のガラガラが置かれる。大晦日前のこの時期は、いつもより景品が奮発される。来るたびにもらえる補助券の束を手にした女の子が若い母親に聞いた。
「一等賞って何?」
「当たったら卒倒するやつや」と母親が言う。
大きな4Kテレビの景品ポスターを見ると、すでに赤いリボン飾りが付いている。選挙の当選者につけるのに似た赤いプラスティックのバラだ。一等や二等が当たると係員が鐘を鳴らして周りの列からも歓声や拍手が起きる。夕方から並んだ僕にはあのテレビはもはや回ってはこない。二等のオーブントースターがちょうどいいと、僕の奥さんは言っていた。それでも持って帰ったら卒倒するかもしれない。ほとほと運がない旦那と思い込んでいる。僕は順番がまわってくる前に十一回分のガラガラの補助券を数えなおしていた。四枚で一回まわせる。一枚足りないからジャージのポケットを探っていると、すぐ前で六回ガラガラをまわし終わった爺さんが、「これ余ってるねん」と補助券の一枚をくれようとした。僕は「こっちの三枚と合わせると一回できるんで、どうぞ」とハンパの三枚を手渡した。「そうか、悪いね」と言って爺さんは一枚から四枚になった補助券を係の人に渡して、もう一回ガラガラをまわした。係の人が鐘をけたたましく鳴らした。二等のトースターにプラスティックのバラをつけて、「おめでとうございます」と爺さんに引換券を渡した。別の係員が奥の棚に案内しようとやってきたとき、爺さんが振り向いて僕に聞いた。
「どうする? にいちゃん、あんた欲しいか」
「どうぞ。おじいさんが当てたんですから」と僕は言った。だいたい僕の人生はこんなものだと、つくづく思う。
母親が熱心だった僕の中学受験は、衆議院選挙が終わったばかりだった。その晩のテレビはどのチャンネルも選挙結果を伝えていた。母親が赤いリボンのバラの意味を教えてくれた。「もしかしたら、受験の面接で選挙のことなんか聞かれるかもしれん」と口にした。選挙のことなんて何も知らない僕は、そんな質問をされたら何と言えばいいんだろうという感じだった。面接の順番がきたとき、
「三月の行事は何ですか」と面接官の一人が聞いた。
「選挙です」と僕は答えた。
三人いた面接官がみんな笑った。意地悪な笑い声ではなかった。楽しそうに笑った。それでも僕は面接点が悪くて、受験に失敗した。今思えば大した挫折でもないが、「ひな祭り」が来るたびに、僕は思い出す。あのとき母さんが選挙って言わなかったら、僕の人生は変わっていただろうか、有名中学に入ったらすっかり違う道が待っていただろうか。普通中学は楽しかった。有名私立なんかでなくてよかったとすぐに思った。だけど、ほんの小さな偶然が道を作っていくのをあのとき見た気がする。重大な事は些細なことで決まる。そんな哲学みたいな考えがまたしても浮かんだ。
この風呂屋には僕の奥さんはついてこない。風呂に入っていると周りの人が目を逸らすから嫌だと言う。片方の乳が無いからだ。乳癌のせいだから仕方なくて、乳房再建手術の方法もあったのだけど、当時は命のことしか考えられなかった。奥さんは、今では片方が無いのに慣れてしまって、転移とかなかったことの方が嬉しいと言う。僕も今ではぺちゃんこになった胸の方が愛おしいくらいだ。だけど唯一、この風呂屋には連れてきたいと思う。スーパー銭湯とかではないけれど、庭に面したところに竹で囲った露天風呂があって、そこのジャグジーに入ると空が見える。大浴場の片隅にはサウナがある。自分で石に水をかけて、八十度を静かに我慢するのが好きだ。ぐっと熱に耐える時間が好きだ。サウナの後の水風呂は最高に気持ちいい。あの入りぎわの自虐的な冷たさと、周りの水に身体が慣れて緩んでいく感覚が好きだ。脱力して解放される。今の僕と同じだ。ただし僕は三ヶ月も脱力している。
繁忙期に職場の床で気を失った。意識が無かったのは、ほんの数秒だったらしいが、産業医から適応障害と診断された。半年の療養休暇が与えられたが、職場に戻るかどうか決めていない。フルタイムに復帰した奥さんは前あきブラにシリコンパッドを入れて、なんだか以前より颯爽と出社している。いつの間にか強い大人の女性になっている。いや、もともとだったのかもしれない。とにかく僕がサウナ好きなのを知っているから、奥さんは風呂屋に行けという。週に三度はここに来る。片胸のない奥さんは家風呂でのんびりしているだろうか。僕が居ない間のびのびしている気もする。
高校時代、イップスになった。高校で弓道部に入った僕は、三年の春に、矢を放ちたくても放つことができなくなった。いわゆる「もたれ」という症状で、弓を引き構え、狙い定めたのに、指が離れてくれない。もうすぐ県大会の日で、二年生の時に三位だった僕は、その三位という成績が最後になった。一位でもなく二位でもなく、三位というのは僕らしい数字だ。今となったら、県大会三位でも自慢話になるんだけれど、「へえー」で終わる話でもある。だけど、奥さんと出会った時、その話をしたら、「それでこんなに肩幅広くて分厚いんだ」と言った。褒められた僕の肩はのぼせあがって、いつになく大胆になった。本当は、運はいいのだ、なんて思いながら、その晩、眠り込んだ奥さんの横顔を見ていた。一位以上の嬉しさだった。
風呂屋の脱衣所で、ジャージを畳んでいると、ポケットの隅に補助券があった。もう用無しの一枚だ。今年の風呂屋は今日が最後だからこれはハンパで終わる。
湯気に霞んだ大風呂はいつもより賑やかで人の声がこだましていた。暮れの大掃除を逃げ出したという背中が笑っている。屋外で凍えたという背中が温まっている。門柱を洗って、門松も飾ったらしい。大晦日に門松を立てるのは縁起が悪いとか誰かが教えているが、驚く様子もない。
「今日まで忙しかってん。二十九日よりマシや」
二十九日は二重苦らしい。そういう縁起話が浴槽の中でしばらく続いた。
一人ものの常連は静かに浸かっている。年の瀬イベント不参加組だ。僕の家はピカピカになっている。ここ一週間で計画的に隅々まで拭きまくり、小さな発見続きだった。隠れた汚れや剥がれ、不具合があちこちにあって、職場から帰った奥さんに元通りに直したことを報告すると、大抵はうるさがられた。だが、研がれた包丁を手にした時は「ああ気持ちいい」と繰り返し言っていた。
入浴のルーティーンを済ませて、ピカピカになった家に帰ろうと靴を履いていると、爺さんの声がした。
「にいちゃん、なんか当たったか」
「四等が三個と、あとは五等でした」
僕は十回分の景品を詰めたビニール袋をふってみせた。
「これと変えよか。重いねん。家遠いし」とオーブントースターの段ボールを抱えた細い腕が持ち上がった。
「僕が持っていってあげましょうか」
「いや、新しいのは何でもめんどくさいし、家には慣れたやつがあって、捨てられへん。うちのバアさんと一緒や」
爺さんはツルツルになった輝く頭をなでながら笑った。
「五等はティッシュですよ。それに四等はフェイスパックだし」
「なんやそれ」
「顔に貼るお面みたいな紙で、肌にいいみたいですよ」と僕はビニール袋の中身を見せて、「僕は使いませんけど、妻が喜ぶかもしれないんで」と付け加えた。
「ほな、そのちっちゃいティッシュだけ貰っとくわ。顔のパックとか持って帰ったら、うちのバアさんアホかって言いよるわ」
結局、僕はトースターの入った段ボールの箱とフェイスパックの入ったビニール袋を下げて、妻のもとに帰った。ことのしだいを話すと、奥さんはいつもより興味深く聞いていた。僕は段ボールから新品のオーブントースターを取り出し、古いオーブントースターを段ボールに入れた。靴箱の横に置きに行って、戻ってみると、奥さんはフェイスパックを貼って、新しいトースターの説明書を読み始めていた。フェイスパックのせいで大人しくしていた口が、かすかに動いて聞いた。
「粗ゴミの回収って新年の四日だったかしら」
「五日のはずだ」と僕は言った。
その晩、遠くから聴こえる除夜の鐘を一緒に数えていた奥さんが寝息を立て始めた。導眠剤のせいで、僕も途中で眠ったようだ。鐘と鐘の間は結構長い。
新しい年の朝がきた。のんびり起きていくと、いつも買っている通販のおせちがテーブルに鮮やかに並んでいた。雑煮の匂いがする。手作りの白味噌の雑煮には大根と人参が入っているはずだ。そこに入れる餅を奥さんが新しいトースターで焼いている。幸せそうな背中が振り返ると、フェイスパックが皺になっていた。何かで笑ったに違いない。
今年は、なんとなく良い年になりそうな気がする。
《『樹林』25年8・9月合併号(通教部作品集)より再掲》
作品寸評
銭湯では年末の抽選会をやっている。「僕」はハンパの補助券三枚を爺さんに手渡し、当たったトースターをあげるという爺さんの申し出をことわる。人がいいというより、愚かなまでのふるまいである。そして「だいたい僕の人生はこんなものだ」と思っている。こういうタイプはたいてい人生の受難者になるが、この作品では小説の魔法によってハッピーエンドがやってくる。深刻にならず、ほんわかと包みこむものがある。乳癌手術。適応障害。イップス。重い話題はペーソスを含みつつも、読者を救いの方向へと導く。後半の細部の積み重ねはすばらしかった。爺さんもいい味を出していた。人生の「重大な事は些細なことで決まる」とあるが、作品の成否も些細なことで決まってくるものだ。この作品は細部の丁寧な積み重ねのうえにメルヘンのような余韻を響かせた。
(高橋達矢)